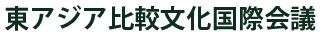開催日:2014年10月25日〜26日 会場:浙江工商大学(杭州)
【総合テーマ】東アジア文化交流――古代文学の共生
◇第1日目◇
開幕式
[司会]李 美子(浙江工商大学日本語言文化学院)
・開会の辞(浙江工商大学日本語言文化学院 王 宝平)
・開会の辞(明星大学 古田島洋介)
・開会の辞(高麗大学校 崔 溶澈)
基調講演
・アスカ攷(京都市立芸術大学名誉教授 中西 進)
・東アジア漢文小説の漢字学研究(天津師範大学文学院 王 暁平)
・十二生肖の文化と民間の俗信(中央大学校 李 澯旭)
研究発表
〈分科会A〉テーマ:古代中日文学交流
[司会]山口敦史(大東文化大学)・宋 再新(四川大学)
・『万葉集』巻一・八番歌の解読からみる万葉集研究の諸問題(四川大学 宋 再新)
・万葉歌人羽栗について(浙江工商大学 呉 玲)
・中世和歌詩体論―「定家十体」における「濃様」を例として―(蘇州大学 李 東軍)
・雪月花と宴席の歌(国学院大学兼任講師 鈴木道代)
・大津皇子の臨終詩(国学院大学大学院生 大谷 歩)
・『日本霊異記』と中国仏教説話(大東文化大学 山口敦史)
・『本朝文粹』の研究(大連外国語大学・天津師範大学 于 永梅)
・「崇玄」と「斥老」―唐日科挙文化における老子思想―(河南師範大学 孫 士超)
・古代交流史と文学―天平五年の遣唐使を中心に―(国学院大学兼任講師 城﨑陽子)
・中日古代女性文学の比較研究―李清照と清少納言を例として―(浙江農林大学 寿舒舒)
〈分科会B〉テーマ:中韓文学交流
[司会]趙 維国(上海師範大学)・朴 美子(熊本大学)
・韓国文学における「漁父」の受容と展開―新羅時代から高麗時代まで―(熊本大学 朴 美子)
・古代文学の共生―『西湖二集』の解読について―(浙江旅游職業学院 翁 嘉)
・韓、中古典小説における性的欲望に関する一考察(復旦大学大学院生 廬 仙娥)
・寓言からみる中、韓公案小説の動物像(高麗大学校大学院生 呉 暁麗)
・『九雲楼(九雲記)』と清初才子佳人小説の比較分析(高麗大学校大学院生 朴 柱娟)
・中国古代小説の東伝と朝鮮早期漢文小説観の成立(上海師範大学 趙 維国)
・韓国英雄小説に受容された中国文化背景の研究(南ソウル大学校 安 圻洙)
・『西遊記』の大蔵と受容の比較文化上の特徴に関する一考察(高麗大学校大学院生 朱 埈永)
・『紅楼夢』と『鏡花縁』の俗語翻訳法について(高麗大学校大学院生 高 明珠)
〈分科会C〉テーマ:中日韓文学交流
[司会]彭 佳紅(帝塚山学院大学)・丹羽博之(大手前大学)
・日中韓国文学における王献之「青氈」逸話の受容(大手前大学 丹羽博之)
・柳宗元「種樹郭橐駝伝」における断句と管到―日中韓漢学の伝統と独自性―(明星大学 古田島洋介)
・韓・中妓女詩歌の比較研究(中央大学校 金 成紋)
・韓・中柱聯詩の比較研究――景福宮、昌徳宮と紫禁城の柱聯を中心に(中央大学校大学院生 陸 佳瑋)
・現代の「かな文学」としての漢詩―夏目漱石、井伏鱒二などの中国古典詩の受容―(帝塚山学院大学 彭 佳紅)
・日本漢詩人北条鴎所と清末上海文人の交際に関する研究(浙江大学 高 平)
・近世初頭堂上文壇の漢詩創作―後陽成院の聯句を中心に―(武蔵野大学 楊 昆鵬)
・近代日本の「古典復興」―正岡子規の「古代発見」を中心に―(浙江理工大学日本学研究所 徐 青)
〈分科会D〉テーマ:中日韓文化交流
[司会]朴 榮俊(中央大学校)・辰巳正明(国学院大学)
・長屋王伝と東アジア文化交流(国学院大学 辰巳正明)
・遣唐使と春日の祭祀―「郊祀」儀礼と東アジア世界―(成城大学 山田直巳)
・絡み合うモチーフ―『大雲寺縁起』成尋の日本での奇瑞をめぐって―(藤女子大学 水口幹記)
・韓日茶道の比較研究(中央大学校 朴 栄俊)
・中日間における朝鮮半島の土公信仰(浙江理工大学 張 麗山)
・朝鮮文人の西域認識(中央大学校 沈 昊南)
〈分科会E〉テーマ:近世・近代中日文化交流
[司会]唐 権(華東師範大学)・丹羽 香(中央学院大学)
・横井小楠の中庸政治思想(同済大学日本学研究所 陳 毅立)
・近代日本知識人の意識に関する一考察(中央学院大学 丹羽 香)
・日本漢学家太田辰夫先生と漢語文法史の研究―言語接触を中心に―(復旦大学 黄 小麗)
・長崎唐通事の語学習得に関する一考察(浙江工商大学 許 海華)
・清末版画における甲午戦争(華東師範大学 唐 権)
・清末雲南赴任の日本教習河合絹吉とその著作『昆明』(浙江工商大学 董 科)
・杭州は日清戦争後なぜ開港場となったのか(京都大学大学院生 王 怡然)
〈浙江工商大学日本語言文化学院・二松学舎大学東アジア学術総合研究所 共同研究シンポジウム〉
テーマ:19・20世紀東アジアの漢学(1900年前後を中心に)
[司会]江藤茂博(二松学舎大学)・王 宝平(浙江工商大学日本語言文化学院)
・船山史論と近代日本の知の再構築―王船山〈宋論〉の日本語訳本〈宋朝史論〉を例として―(南開大学日本研究院 劉 岳兵)
・津田左右吉と長谷川如是閑の『老子』思想の研究(浙江万里学院日本語学科 郭 永恩)
・明治時代の日本漢文学家依田学海と中国―在日外交官との交流を中心に―(周口師範学院 楊 爽)
・文と文学と文学史―近代における漢学の意義―(二松学舎大学 牧角悦子)
・1900年前後の漢学界の動向―島田重礼を中心に―(二松学舎大学 町泉寿郎)
・共同討議 明治期日本の漢学と漢学者
◇第2日目◇
記念講演
・白居易詩と菅原道真詩と―湖上詩を中心として―(国学院大学 波戸岡 旭)
・明治前期における中国渡航の韓文学者と上海の文人達―北条鴎所を中心に―(浙江工商大学日本語言文化学院 王 宝平)
・近代日本学校制度における「漢学」と「漢字」(二松学舎大学 江藤茂博)
・朝鮮時代『漂海録』における中国南方描写(高麗大学校 崔 溶澈)
閉会式
・挨拶(王 勇)
・挨拶(中央大学校 李 澯旭)
・挨拶(国学院大学 辰巳正明)
・挨拶(浙江工商大学日本語言文化学院 王 宝平)